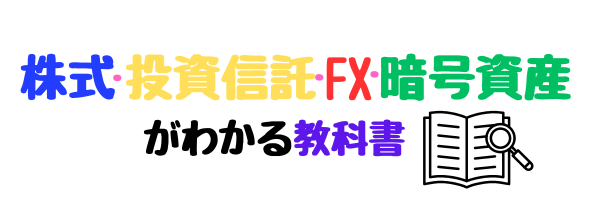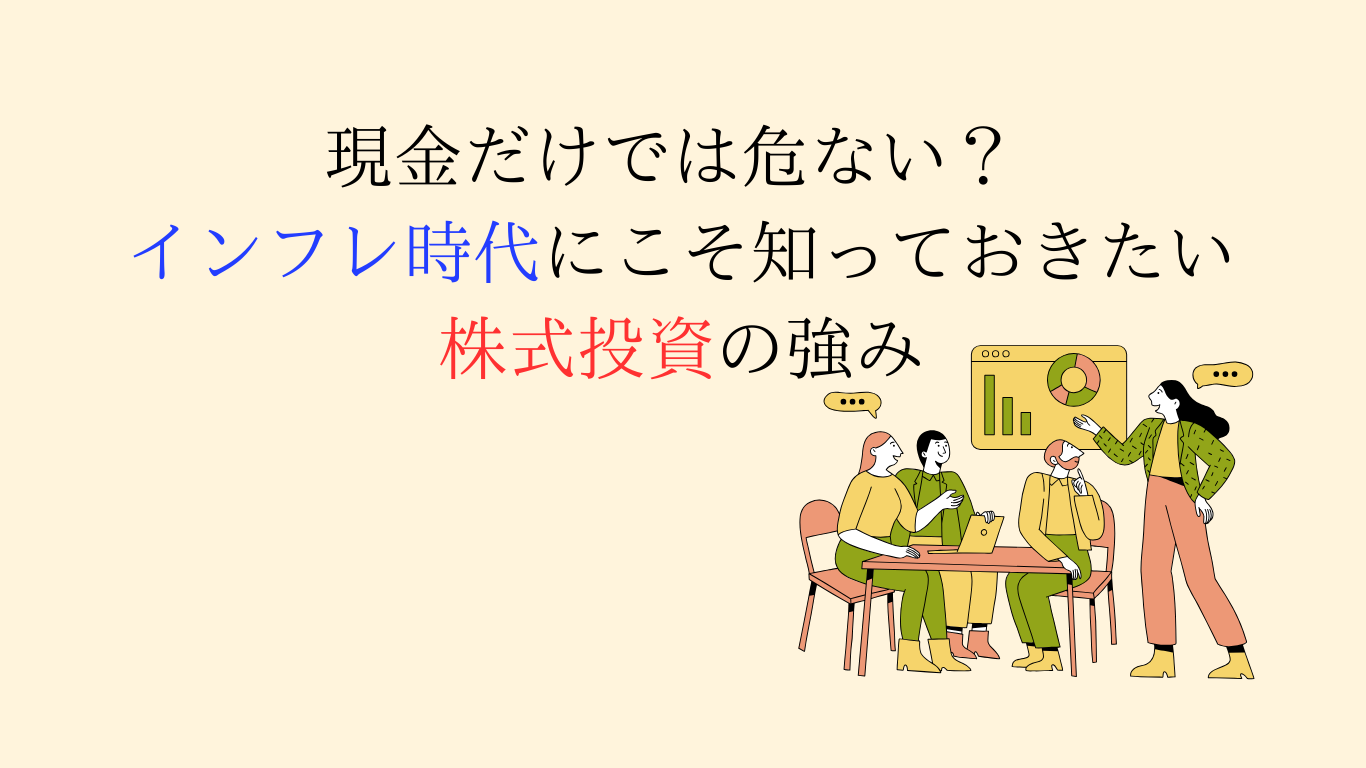インフレが資産に及ぼす影響とは?
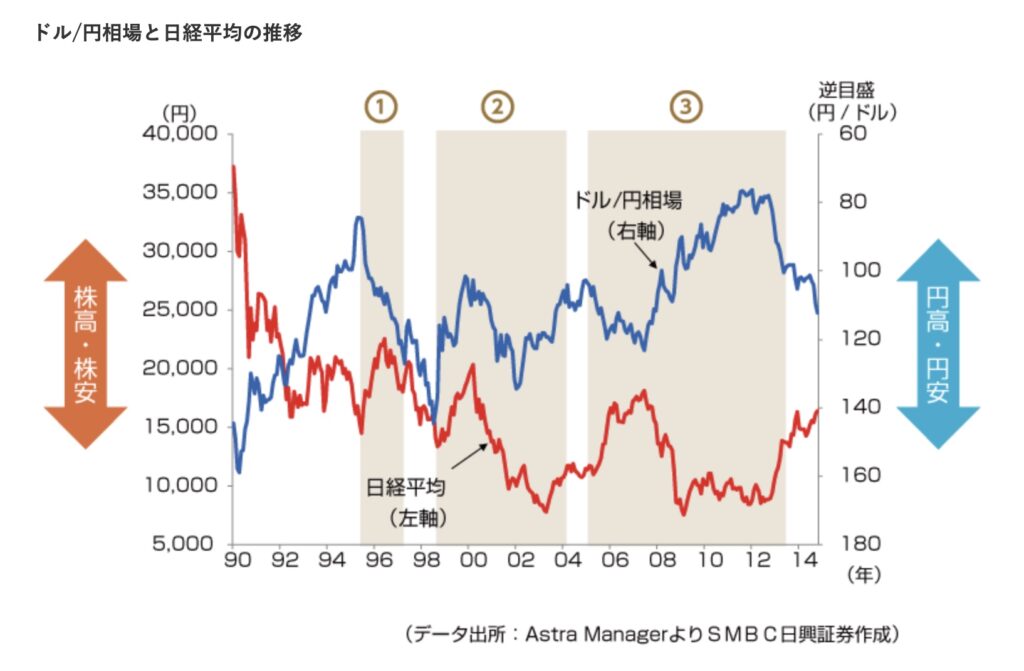
● お金の価値=「購買力」が下がる
インフレ(物価上昇)が続くと、同じ商品やサービスを買うのに、より多くのお金が必要になります。たとえば、100円で買えていたものが、数年後には110円や120円になっているかもしれません。これは、お金の価値(購買力)が下がっていることを意味します。
● 銀行預金の実質価値が目減りする
日本では長らく低金利が続き、銀行預金の金利はごくわずかです。仮にインフレ率が2%上昇しているのに、預金金利が0.1%程度ならば、預けているだけで実質的に1.9%の価値が失われる計算になります。数字上の口座残高は変わらなくても、モノやサービスを買える力(購買力)は確実に落ちるのです。
● 資産運用の必要性が高まる
インフレ環境では、現金だけを保有していると資産を守ることが難しくなります。こうした状況の中、「株式投資」をはじめとする資産運用の重要性が増してきます。
なぜ株式投資はインフレに強いと言われるのか
企業利益の増加につながる可能性
インフレが進行すると、企業は原材料コストや人件費が上がる一方で、商品やサービスの価格を値上げすることでそれを転嫁しようとします。特に、生活必需品や独自ブランドを持つ企業は比較的値上げが受け入れられやすく、売上高や利益の増加につながる場合が多いのです。
結果として企業の業績が向上すれば、株価が上昇する可能性も高まります。
企業が保有する資産価値の上昇
企業は不動産、特許、ブランドなどの有形・無形資産を保有しています。これらの資産価値はインフレに伴って上がることが少なくありません。たとえば、不動産価格が上昇すると、そのぶん企業の評価額(バリュエーション)にもプラスの影響が及び、株価が下支えされる要因になります。
他の金融資産に比べて実質的なリターンが得やすい
インフレ局面で金利が上昇すると、債券の価値は下がりやすくなります。一方、株式は企業利益に連動して配当金や株価が上昇する可能性があるため、インフレを上回るリターンを得やすい資産として注目されています。
インフレ時代に株式投資を始めるメリット
 よし・個人投資家
よし・個人投資家新NISA枠を使うと儲けが非課税です。
- 資産の目減りリスクを抑えられる
インフレ下でも成長が期待できる企業に投資しておくと、通貨価値の下落をある程度相殺できます。長期的に見れば、株価や配当収入によってインフレ率以上のリターンを狙える可能性があります。 - 経済成長の恩恵を受けられる
インフレは多くの場合、ある程度の経済成長を伴うことが一般的です。企業業績が良くなると、株主としてその恩恵を受けやすいのが株式投資です。 - 多様な投資戦略がとれる
株式投資には、値上がり益を狙うだけでなく、配当や株主優待を得る戦略も存在します。銘柄選定や保有期間など、自分の投資スタイルに応じた戦略を組み立てられる柔軟性も魅力です。
インフレ時代におすすめのアクションプラン
株式投資をまったく経験したことがない方は、まずは証券口座を開設し、少額から投資を始めてみましょう。NISA(少額投資非課税制度)など税制優遇制度を利用すると、運用益や配当にかかる税金が非課税になるメリットもあります。
毎月一定額をコツコツ投資する「積立投資」は、株価が上下する局面でも取得単価を平準化できるメリットがあります。ドル・コスト平均法を活用し、長期的にリターンを狙うのが王道の手法といえるでしょう。
生活必需品、エネルギー、インフラ関連、ブランド力の高い消費財など、比較的インフレに強いとされる企業・セクターを検討してみるのも一つの方法です。
インフレ率や金利動向、世界経済の状態は常に変化しています。投資スタイルに合ったリスク許容度と目標を設定し、数か月~数年ごとにポートフォリオを見直すことで、時代の変化に適応し続けることができます。
まとめ:インフレに強い資産形成のカギは「株式投資」にあり
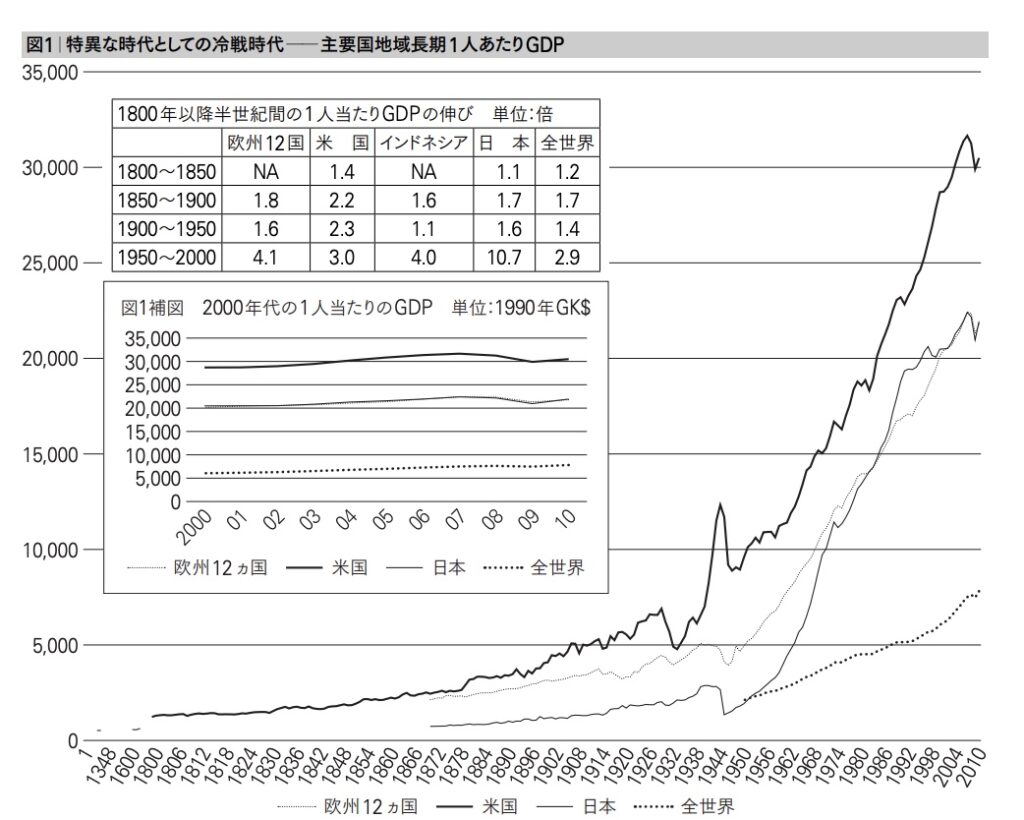
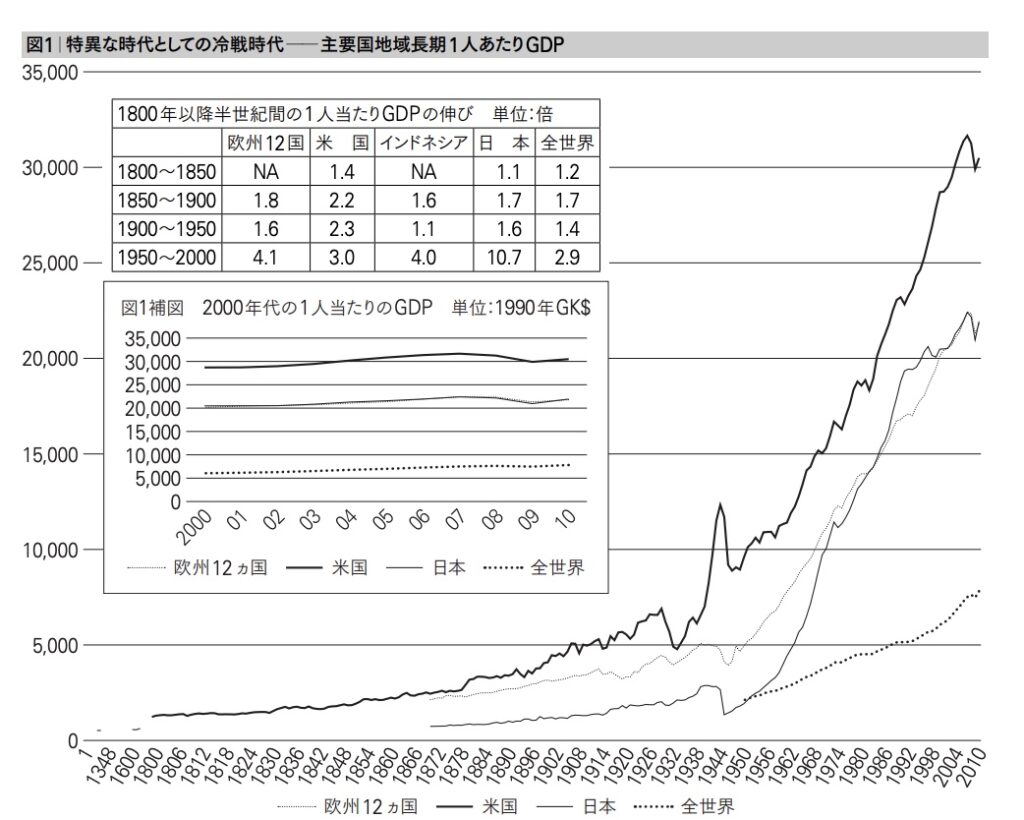
- 現金の価値はインフレで目減りしやすい
銀行預金では物価上昇に追いつかない可能性が高く、資産の実質的な価値が下がりやすい。 - 株式投資は企業利益や資産価値の上昇を取り込める
価格転嫁が可能なビジネスモデルや、実物・無形資産を多く保有する企業はインフレ時代に強さを発揮しやすい。 - ただし、分散投資とリスク管理が必須
すべての企業がインフレに対応できるわけではなく、短期的な相場変動リスクも考慮する必要がある。